2013年02月25日
第一次上田合戦
天正十二年(一五八四)、織田信長亡き後の覇権をめぐって、徳川家康は豊臣秀吉との対立を深めていた。家康は北条氏との連携を深め、昌幸に対し沼田城を北条に引き渡すように命じてきた。昌幸はこの命令を拒み、それまで臣従していた家康から離れ、越後の上杉景勝に近づいた。次男信繁を証人(人質)として海津城に送った。
家康はこの事態に激怒し、真田攻めを決意する。天正十三年八月、徳川方は鳥居元忠・大久保忠世・平岩親吉に七〇〇〇の大軍を付け上田を攻めた。対する真田方は二〇〇〇人ほどの兵力であった。戦いは国分寺付近の神川の河原を主戦場に行われた。
昌幸は得意の奇襲戦法で徳川方を翻弄し、ついには家康を信濃から追い払った。この戦いに参戦した信之(当時は信幸)は「去る二日、国分寺において一戦をとげ、千三百余討ち捕り」と沼田城に手紙を送っている。
その後昌幸は、上杉景勝を通して秀吉に臣従していく。天正十三年、昌幸は信幸と信繁(幸村)を伴って大坂に上り、秀吉に謁見している。しかし、老獪な秀吉は心底から昌幸を信頼してはいなかったようで、家康に真田攻めを促すなど、実力者家康を懐柔するために昌幸に対する距離を微妙に変えている。
天正十四年(一五八六)十月、家康は上洛し秀吉に謁見する。ついに秀吉は最大のライバルである家康を臣従させることに成功したのである。その見返りに秀吉は、昌幸が家康の臣下となるよう命じた。昌幸は翌年三月、駿府城に出仕する。天正十七年(一五八九)には昌幸の長男信幸も駿府城に出仕した。
天下統一を目指す秀吉は家康を味方につけたことで、残る敵は小田原の北条氏直だけとなった。氏直は上洛の条件として、真田が領有する沼田領の引き渡しを要求してきた。
天正十七年七月、秀吉は沼田領の三分の二を北条に引き渡すという裁定を下した。その代わりとして真田には信濃に新しい領土が宛がわれた。昌幸はこの裁定に従った。今秀吉を敵に回すことは得策ではないと考えたのだろう。
しかし、その年の十一月になって沼田城にあった北条の将兵が突然真田領の名胡桃(なぐるみ)城を奇襲した。これが秀吉の北条攻めの理由となった。翌年一月、秀吉は二〇万という大軍を率いて小田原攻めに下った。昌幸もこれに従った。天正十八年七月、小田原城は落ち、北条氏は滅亡した。
北条氏の滅亡により秀吉の天下統一の事業はほぼ完成した。家康は関東に移され、北条氏の旧領が与えられた。家康麾下の信濃の領主たちの多くが関東に移されるなか、昌幸は秀吉から小県の旧領が安堵された。長男の信幸は家康から沼田領を安堵された。この間信幸は家康の重臣である本多忠勝の娘小松姫を娶り家康への接近を強め。信繁(幸村)は秀吉の家臣である大谷刑部義継の娘を妻とし秀吉との関係を強めていった。
慶長三年(一五九八)に秀吉が亡くなるまで、真田家は平穏な時代を過ごした。天正十九年(一五九一)の朝鮮出兵はあったが、この間上田の城下町の整備が進んだものと思われる。近年になって上田城址から当時のものと思われる金箔瓦が出土している。本格的な城郭が築かれていたのであろう。
家康はこの事態に激怒し、真田攻めを決意する。天正十三年八月、徳川方は鳥居元忠・大久保忠世・平岩親吉に七〇〇〇の大軍を付け上田を攻めた。対する真田方は二〇〇〇人ほどの兵力であった。戦いは国分寺付近の神川の河原を主戦場に行われた。
昌幸は得意の奇襲戦法で徳川方を翻弄し、ついには家康を信濃から追い払った。この戦いに参戦した信之(当時は信幸)は「去る二日、国分寺において一戦をとげ、千三百余討ち捕り」と沼田城に手紙を送っている。
その後昌幸は、上杉景勝を通して秀吉に臣従していく。天正十三年、昌幸は信幸と信繁(幸村)を伴って大坂に上り、秀吉に謁見している。しかし、老獪な秀吉は心底から昌幸を信頼してはいなかったようで、家康に真田攻めを促すなど、実力者家康を懐柔するために昌幸に対する距離を微妙に変えている。
天正十四年(一五八六)十月、家康は上洛し秀吉に謁見する。ついに秀吉は最大のライバルである家康を臣従させることに成功したのである。その見返りに秀吉は、昌幸が家康の臣下となるよう命じた。昌幸は翌年三月、駿府城に出仕する。天正十七年(一五八九)には昌幸の長男信幸も駿府城に出仕した。
天下統一を目指す秀吉は家康を味方につけたことで、残る敵は小田原の北条氏直だけとなった。氏直は上洛の条件として、真田が領有する沼田領の引き渡しを要求してきた。
天正十七年七月、秀吉は沼田領の三分の二を北条に引き渡すという裁定を下した。その代わりとして真田には信濃に新しい領土が宛がわれた。昌幸はこの裁定に従った。今秀吉を敵に回すことは得策ではないと考えたのだろう。
しかし、その年の十一月になって沼田城にあった北条の将兵が突然真田領の名胡桃(なぐるみ)城を奇襲した。これが秀吉の北条攻めの理由となった。翌年一月、秀吉は二〇万という大軍を率いて小田原攻めに下った。昌幸もこれに従った。天正十八年七月、小田原城は落ち、北条氏は滅亡した。
北条氏の滅亡により秀吉の天下統一の事業はほぼ完成した。家康は関東に移され、北条氏の旧領が与えられた。家康麾下の信濃の領主たちの多くが関東に移されるなか、昌幸は秀吉から小県の旧領が安堵された。長男の信幸は家康から沼田領を安堵された。この間信幸は家康の重臣である本多忠勝の娘小松姫を娶り家康への接近を強め。信繁(幸村)は秀吉の家臣である大谷刑部義継の娘を妻とし秀吉との関係を強めていった。
慶長三年(一五九八)に秀吉が亡くなるまで、真田家は平穏な時代を過ごした。天正十九年(一五九一)の朝鮮出兵はあったが、この間上田の城下町の整備が進んだものと思われる。近年になって上田城址から当時のものと思われる金箔瓦が出土している。本格的な城郭が築かれていたのであろう。
2013年02月24日
上田城
勝頼自害の報を聞いた昌幸は、変わり身早く信長に忠誠を誓う。ところがそれからまもなく、信長は明智光秀の奇襲を受け本能寺で自害してしまう。信長死後の東信濃は徳川・上杉・北条の勢力争いの場となった。その中で真田昌幸は臣従する相手を次々と変えながら生き残る術を探っていた。
最初は上野の領地を死守したいという思いからか北条氏に誼を通じていたが、武田氏滅亡後徳川氏の臣となっていた弟の加津野信昌、依田信蕃の勧誘を受けて徳川家康に従うこととなった。
天正十一年(一五八三)昌幸は、それまで本拠としていた戸石城から現在の上田城址のある尼ヶ淵に築城を開始した。真田の里に比べるとこのあたりは気候は温暖であり、平地も多い。上田は気候の厳しい信州のなかでも比較的暮らしやすい町である。碓氷峠を上り新幹線は、軽井沢から佐久、上田と徐々に標高を下げ、そのぶんだけ気候も温暖なものになる。
上田から、善光寺平を北に向かうと、こんどは冬の積雪が心配になる。上田は長野に比べてもずいぶんと積雪量の少ない町なのである。菅平の麓の山間の地を根拠地としていた真田氏としても、なんとか千曲河畔の上田のあたりまで領土を広げたいものだとの野望を抱き続けていたことであろう。
昌幸の築いた城は、ほぼ現在の上田城址の場所と重なる。千曲川の河岸段丘上に築かれ、南側は険しい崖となっており、崖下を千曲川の支流である尼ヶ淵が洗っており、築城当時は尼ヶ淵城ともよばれていた。
真田氏にとって、上州における敵は北条氏であったが、信濃にあっては上杉氏であった。信長の死後、川中島を領有していた森長可は逃げてしまい、代わって進出してきたのが上杉景勝であった。景勝は上田と川中島との国境に連なる虚空蔵山に砦を築き、真田を牽制していた。
最初は上野の領地を死守したいという思いからか北条氏に誼を通じていたが、武田氏滅亡後徳川氏の臣となっていた弟の加津野信昌、依田信蕃の勧誘を受けて徳川家康に従うこととなった。
天正十一年(一五八三)昌幸は、それまで本拠としていた戸石城から現在の上田城址のある尼ヶ淵に築城を開始した。真田の里に比べるとこのあたりは気候は温暖であり、平地も多い。上田は気候の厳しい信州のなかでも比較的暮らしやすい町である。碓氷峠を上り新幹線は、軽井沢から佐久、上田と徐々に標高を下げ、そのぶんだけ気候も温暖なものになる。
上田から、善光寺平を北に向かうと、こんどは冬の積雪が心配になる。上田は長野に比べてもずいぶんと積雪量の少ない町なのである。菅平の麓の山間の地を根拠地としていた真田氏としても、なんとか千曲河畔の上田のあたりまで領土を広げたいものだとの野望を抱き続けていたことであろう。
昌幸の築いた城は、ほぼ現在の上田城址の場所と重なる。千曲川の河岸段丘上に築かれ、南側は険しい崖となっており、崖下を千曲川の支流である尼ヶ淵が洗っており、築城当時は尼ヶ淵城ともよばれていた。
真田氏にとって、上州における敵は北条氏であったが、信濃にあっては上杉氏であった。信長の死後、川中島を領有していた森長可は逃げてしまい、代わって進出してきたのが上杉景勝であった。景勝は上田と川中島との国境に連なる虚空蔵山に砦を築き、真田を牽制していた。
2013年02月21日
不要不急
以前にも書いたのですが、古本屋というのは天候に左右される商売です。それも天気の悪い日は確実にお客は来ないのですが、天気がいいからといって確実にお客がくるわけではない。それは商っている商品、すなわち古本が不要不急の商品だからでしょう。
かつてこの辺りを走っていた善白鉄道というのが、戦争中に不要不急路線ということで休止命令を受け、その列車やレールは南方の戦地に送られました。さしずめ古本屋は戦争でも起これば不要不急商品として店は閉鎖され、竹槍工場にでもなるのかもしれません。古本を商うものとしてこれは誇るべきことなのかもしれません。戦争には不要不急であることはいいことです。
一方で原子力発電というのが戦後の日本では原爆反対運動へのアンチキャンペーンとして、某大新聞社などが音頭を取り大々的に喧伝されたという経緯があります。原子力発電は確かに原子力の平和利用として実に有効なのかもしれません。しかしこれは戦争になれば実に有効な技術でもあるわけだし、平和時においても危険なものであることがわかりました。安倍さんはアメリカに行って、オバマ大統領との会談で原発ゼロの方針を見直すことを伝えるようです。私はこの一点だけで安倍内閣は支持しません。
たとえ景気がよくなろうがバブルが起きようがダメなものはダメ、ならぬものはならぬのです。まあ、景気が良くなったからといって古本屋は繁盛しません。天気が良くても古本屋に客が来るわけではないのと一緒です。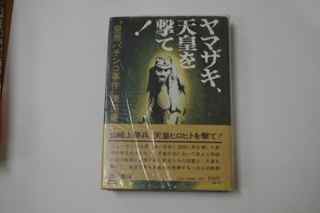
かつてこの辺りを走っていた善白鉄道というのが、戦争中に不要不急路線ということで休止命令を受け、その列車やレールは南方の戦地に送られました。さしずめ古本屋は戦争でも起これば不要不急商品として店は閉鎖され、竹槍工場にでもなるのかもしれません。古本を商うものとしてこれは誇るべきことなのかもしれません。戦争には不要不急であることはいいことです。
一方で原子力発電というのが戦後の日本では原爆反対運動へのアンチキャンペーンとして、某大新聞社などが音頭を取り大々的に喧伝されたという経緯があります。原子力発電は確かに原子力の平和利用として実に有効なのかもしれません。しかしこれは戦争になれば実に有効な技術でもあるわけだし、平和時においても危険なものであることがわかりました。安倍さんはアメリカに行って、オバマ大統領との会談で原発ゼロの方針を見直すことを伝えるようです。私はこの一点だけで安倍内閣は支持しません。
たとえ景気がよくなろうがバブルが起きようがダメなものはダメ、ならぬものはならぬのです。まあ、景気が良くなったからといって古本屋は繁盛しません。天気が良くても古本屋に客が来るわけではないのと一緒です。
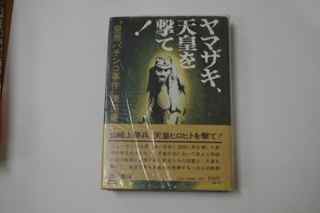
Posted by 南宜堂 at
09:20
│Comments(0)
2013年02月20日
勝頼の最期
これより先、勝頼は二月二十八日に諏訪から新府城に戻っていたが、高遠落城の知らせに城内は混乱の極みとなった。最早織田軍が甲斐に攻め入るのは時間の問題、家臣たちは浮き足立っていた。真田昌幸はこの時自領の吾妻に居たが、使者を送って勝頼にひとまずは兵をまとめて岩櫃の城に逃れるようにと勧めたという。しかし勝頼はその申し入れを退け、近臣である小山田信茂の居城である岩殿城に逃れることを決めた。
翌三日、勝頼の一行は新府城を後に岩殿城を目指して出発した。しかし、馬も人足も満足に揃えることができず、勝頼夫人は輿ではなく、馬に乗っての道行きであった。
一行は柏尾、駒飼と追っ手を避けながら進んだ。三月五日、笹子峠の麓駒飼にたどりついた勝頼らはここで小山田信茂からの迎えを待った。しかしこの時、小山田信茂は勝頼に見切りをつけていた。あろうことか、人質として留めてあった信茂の母が、武田左衞門(信玄の弟で信茂の婿)の手引きにより逃げ出してしまったのだ。慌てて後を追うと、待ち伏せていた小山田の兵が鉄砲を撃ちかけてきた。
信茂に裏切られたことを知った勝頼は、もはやこれまでと覚悟を決めた。十一日の朝、滝川一益が数千の兵を率いて攻めかかってきた。対する勝頼の陣は五十人、とても勝ち目はなかった。勝頼と夫人はここで自害し、付き従う者たちもすべて討ち死にした。戦国の雄武田氏はここに滅びたのである。
勝頼自害の報を聞いた昌幸は、四月八日には変わり身早く信長に駿馬を贈って忠誠を誓った。ところがそれからまもない六月二日、信長は明智光秀の奇襲を受け本能寺で自害してしまう。信長死後の東信濃は徳川・上杉・北条の勢力争いの場となった。その中で真田は臣従する相手を次々と変えながら生き残る術を探っていた。
翌三日、勝頼の一行は新府城を後に岩殿城を目指して出発した。しかし、馬も人足も満足に揃えることができず、勝頼夫人は輿ではなく、馬に乗っての道行きであった。
一行は柏尾、駒飼と追っ手を避けながら進んだ。三月五日、笹子峠の麓駒飼にたどりついた勝頼らはここで小山田信茂からの迎えを待った。しかしこの時、小山田信茂は勝頼に見切りをつけていた。あろうことか、人質として留めてあった信茂の母が、武田左衞門(信玄の弟で信茂の婿)の手引きにより逃げ出してしまったのだ。慌てて後を追うと、待ち伏せていた小山田の兵が鉄砲を撃ちかけてきた。
信茂に裏切られたことを知った勝頼は、もはやこれまでと覚悟を決めた。十一日の朝、滝川一益が数千の兵を率いて攻めかかってきた。対する勝頼の陣は五十人、とても勝ち目はなかった。勝頼と夫人はここで自害し、付き従う者たちもすべて討ち死にした。戦国の雄武田氏はここに滅びたのである。
勝頼自害の報を聞いた昌幸は、四月八日には変わり身早く信長に駿馬を贈って忠誠を誓った。ところがそれからまもない六月二日、信長は明智光秀の奇襲を受け本能寺で自害してしまう。信長死後の東信濃は徳川・上杉・北条の勢力争いの場となった。その中で真田は臣従する相手を次々と変えながら生き残る術を探っていた。
2013年02月18日
会津と高遠
長篠の戦いの敗北は、武田滅亡の序曲であった。武田勝頼はその敗北の影響を最小限に食い止めようと躍起となった。そのひとつの現れが新府城の建設である。父信玄は生涯城を築こうとはしなかった。「人は石垣、人は城」、人材こそが国を護る城であると考えていた。信玄と勝頼、その大将としての器の違いが家臣たちの離反を招いた。
天正十年春、木曽義昌が織田方に寝返った。義昌の領地は織田との国境に近い木曽、常に攻め入られる危険にさらされていた。そんな義昌がまず勝頼に反旗を翻したのである。義昌謀反の報を受けた武田勝頼は、従兄弟である武田信豊(川中島の戦いで戦死した典厩信繁の嗣子)をして木曽に攻め入らせたが、鳥井峠で義昌の兵に押し返された。
勝頼は二月二日諏訪に兵を進めて上原城に着陣した。一方の織田方は二月三日に信濃に攻め入ってきた。守る伊那の諸将は士気が上がらず、松尾城主小笠原信嶺は織田に内応した。信嶺の内応により織田方は難なく下伊那を平定し、伊那谷を攻め上った。
三月二日、信長の嫡男信忠を大将とする織田軍は高遠城を攻めた。この城を守るのは仁科五郎盛信、信玄の五男である。盛信は父信玄の命により信濃安曇の名家仁科氏を継いでいた。勝頼の代になって、織田・徳川への備えとして高遠城の城主となっていたのである。攻める織田は五万の兵、護る武田方はわずか三千という圧倒的な兵力の差があった。信忠は盛信に使者を送り降伏を勧告した。しかし、盛信はこれには応じず使者の耳をそぎ落として帰したという。数に勝る織田軍は難なく城内に攻め入り、盛信以下城に籠もる兵たちは女子どもも含めて玉砕した。
この時、盛信を助けて奮戦したのが保科正直であった。保科氏はもともとは高遠城主高遠氏の家臣であったが、天文二十一年に武田信玄に攻められ高遠氏は滅亡した。正直の父正俊はこの時武田氏の傘下に入った。正直は落城に際して落ち延び、織田信長が本能寺の変で倒れると、高遠城の奪還に成功している。その後は徳川家康に仕え、高遠領を安堵された。正直の子正光は、家康の関東入府により下総多胡に領地を与えられたが、関ヶ原の戦いの後は旧領高遠に戻り二万五千石を給された。その後大坂の陣で軍功を上げ三万石に加増されている。この正光の養子となったのが保科正之である。その保科正之は、出羽に移封となるに当たり、保科家の家臣を多数引き連れていった。その中には高遠城の落城の時に死にものぐるいで奮戦したものたちの子孫も含まれていた。
武田家滅亡に際し、組織的な抵抗を試みたのは仁科信盛と高遠の兵たちだけであった。戊辰戦争に際しても、最期まで抵抗を続けたのは会津藩の兵たちだけであった。この暗合を柴田錬三郎が指摘しているが、まさに保科正之が会津の地に植え付けたのは、高遠武士の最後の一兵まで戦うという玉砕の精神であったのだという。
高遠にある保科正之像

天正十年春、木曽義昌が織田方に寝返った。義昌の領地は織田との国境に近い木曽、常に攻め入られる危険にさらされていた。そんな義昌がまず勝頼に反旗を翻したのである。義昌謀反の報を受けた武田勝頼は、従兄弟である武田信豊(川中島の戦いで戦死した典厩信繁の嗣子)をして木曽に攻め入らせたが、鳥井峠で義昌の兵に押し返された。
勝頼は二月二日諏訪に兵を進めて上原城に着陣した。一方の織田方は二月三日に信濃に攻め入ってきた。守る伊那の諸将は士気が上がらず、松尾城主小笠原信嶺は織田に内応した。信嶺の内応により織田方は難なく下伊那を平定し、伊那谷を攻め上った。
三月二日、信長の嫡男信忠を大将とする織田軍は高遠城を攻めた。この城を守るのは仁科五郎盛信、信玄の五男である。盛信は父信玄の命により信濃安曇の名家仁科氏を継いでいた。勝頼の代になって、織田・徳川への備えとして高遠城の城主となっていたのである。攻める織田は五万の兵、護る武田方はわずか三千という圧倒的な兵力の差があった。信忠は盛信に使者を送り降伏を勧告した。しかし、盛信はこれには応じず使者の耳をそぎ落として帰したという。数に勝る織田軍は難なく城内に攻め入り、盛信以下城に籠もる兵たちは女子どもも含めて玉砕した。
この時、盛信を助けて奮戦したのが保科正直であった。保科氏はもともとは高遠城主高遠氏の家臣であったが、天文二十一年に武田信玄に攻められ高遠氏は滅亡した。正直の父正俊はこの時武田氏の傘下に入った。正直は落城に際して落ち延び、織田信長が本能寺の変で倒れると、高遠城の奪還に成功している。その後は徳川家康に仕え、高遠領を安堵された。正直の子正光は、家康の関東入府により下総多胡に領地を与えられたが、関ヶ原の戦いの後は旧領高遠に戻り二万五千石を給された。その後大坂の陣で軍功を上げ三万石に加増されている。この正光の養子となったのが保科正之である。その保科正之は、出羽に移封となるに当たり、保科家の家臣を多数引き連れていった。その中には高遠城の落城の時に死にものぐるいで奮戦したものたちの子孫も含まれていた。
武田家滅亡に際し、組織的な抵抗を試みたのは仁科信盛と高遠の兵たちだけであった。戊辰戦争に際しても、最期まで抵抗を続けたのは会津藩の兵たちだけであった。この暗合を柴田錬三郎が指摘しているが、まさに保科正之が会津の地に植え付けたのは、高遠武士の最後の一兵まで戦うという玉砕の精神であったのだという。
高遠にある保科正之像

Posted by 南宜堂 at
23:47
│Comments(0)





