2011年09月29日
「男はつらいよ」3本立て
店が暇なものだから、「男はつらいよ」シリーズのDVDを3本も見てしまった。流石にこれだけ見るとつかれてしまう。かつての京一会館、4本立て200円を見た日々を思い出してしまった。
いずれも昭和50年代前半に撮られたもので、私にとってはまだ20代、久々に長野に帰り、就職したころのことだ。まだこの頃の日本にはあんな懐かしい風景が残っていたのだ。 と思ったのだが、山田洋次監督はそんな風景が無くなっていくからこそ、必死になって懐かしい風景が残る場所を探し、映画を撮ったのだろう。
30年以上が過ぎて、私たちはその映画をDVDというほんの薄っぺらな円盤で楽しめるようになった。旅先で、10円玉の落ちる音を気にしなくとも電話がかけられるようになった。バスはワンマンになり、タバコやジュースも自動販売機で買えるようになった。一晩中開いているコンビニというものがあたりまえの存在となった。
それでもあの映画を見て懐かしいと感じ、あの頃の方が良かったと感ずるのはなぜなのだろうか。人間の習性として、嫌なことは忘れ、いいことだけが思い出として残るのだということを聞いたことがある。それでなければ人は生きていくのに耐えられないのだと。
あの頃の日本はいまだ貧しく、離島や山間部の生活は不便極まりなかった。だからこそ私たちは必死に働き、都会に出た。そんな生活から脱却しようとしたのだ。 山田洋次監督はその時代にそれは少し違うんじゃないかと思い、映画の中に古い日本の風景を描くことでそのことを伝えようとしたのだろう。
30年以上が過ぎて、映画を見ている私たちは山田監督のメッセージをどう受け止めるのか。便利さや豊かさを捨てても懐かしい風景の中で暮らしたいと思うのか。古本屋をやっているのだから、答えは出ているはずなのだが、それでも迷うのである。DVDもパソコンも捨てることはできないし。
さて、高遠で古本屋をやっておられた仙人Oさんが、ブログで長野の一箱古本市のことを紹介してくださっている。その時、小布施での古本屋再開をつん堂さんが勧めておられた。小布施はいい町で、古本屋が似合うとは思うのだが、観光地であるので家賃に見合うだけのお客さんが来るかということがネックだと思う。
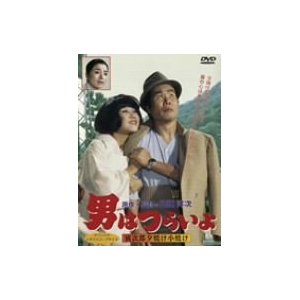
いずれも昭和50年代前半に撮られたもので、私にとってはまだ20代、久々に長野に帰り、就職したころのことだ。まだこの頃の日本にはあんな懐かしい風景が残っていたのだ。 と思ったのだが、山田洋次監督はそんな風景が無くなっていくからこそ、必死になって懐かしい風景が残る場所を探し、映画を撮ったのだろう。
30年以上が過ぎて、私たちはその映画をDVDというほんの薄っぺらな円盤で楽しめるようになった。旅先で、10円玉の落ちる音を気にしなくとも電話がかけられるようになった。バスはワンマンになり、タバコやジュースも自動販売機で買えるようになった。一晩中開いているコンビニというものがあたりまえの存在となった。
それでもあの映画を見て懐かしいと感じ、あの頃の方が良かったと感ずるのはなぜなのだろうか。人間の習性として、嫌なことは忘れ、いいことだけが思い出として残るのだということを聞いたことがある。それでなければ人は生きていくのに耐えられないのだと。
あの頃の日本はいまだ貧しく、離島や山間部の生活は不便極まりなかった。だからこそ私たちは必死に働き、都会に出た。そんな生活から脱却しようとしたのだ。 山田洋次監督はその時代にそれは少し違うんじゃないかと思い、映画の中に古い日本の風景を描くことでそのことを伝えようとしたのだろう。
30年以上が過ぎて、映画を見ている私たちは山田監督のメッセージをどう受け止めるのか。便利さや豊かさを捨てても懐かしい風景の中で暮らしたいと思うのか。古本屋をやっているのだから、答えは出ているはずなのだが、それでも迷うのである。DVDもパソコンも捨てることはできないし。
さて、高遠で古本屋をやっておられた仙人Oさんが、ブログで長野の一箱古本市のことを紹介してくださっている。その時、小布施での古本屋再開をつん堂さんが勧めておられた。小布施はいい町で、古本屋が似合うとは思うのだが、観光地であるので家賃に見合うだけのお客さんが来るかということがネックだと思う。
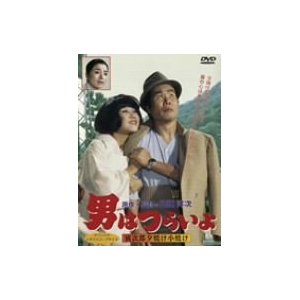
2011年09月27日
つん堂文庫のこと
昨日小山清について書いた記事について、私は決して小山の作品が嫌いということではない。むしろ好きな作家ではあるのだが、古書価格が高いので一言言いたかったのだ。
さて、そこでも述べたつん堂文庫のこと。それほど大げさなものではなく、長野の古本市で残った本をお預かりしたということ、せっかくだからそれを店に並べましょうということになったという次第なのである。自分の集めた本の反応を見たいというつん堂さんの希望もあった。
私どもとしても、つん堂さんの選んだ本ならぜひ置かせていただきたいということで、つん堂文庫開設の運びとなったものである。大書店の丸善と光風舎を比較したのでは気がひけるのだが、松丸本舗のようなものを実はイメージしているのである。
愛書家のつん堂さんのことについては、ここでいろいろ説明するよりはご自身のブログを見ていただくのがいいと思う。光風舎との縁は、古本屋ツアーさんの記事に興味を覚え、訪れたこの店が気に入っていただいたということからだと思う。最初の印象をつん堂さんのブログから引用すると、
「店内もしんしんとして、じっくり本を選ぶにはつらい。
ただし、店内はきれいに整理され、良書がぎっしりとうれしい状況。だけど、だけど、うまくはいきません。まず、好みが一致しすぎて、所持本とカブリがほとんど。しかも、値段はしっかりついている。こうなるとなかなか手が伸びないものです。」(1月13日付)
その後、仕事の関係で長野出張の多いつん堂さんは、時々光風舎に来ていただくようになった。つん堂さんは親切な方で、東京の古本事情に疎い私たちにいろいろと話してくださり、先月の「あいおい古本まつり」では東京の愛書家の方たちをご紹介いただき、ご一緒に食事をさせていただいた。
ただ、あくまでも客と店主という関係だからお互いプライベートなことは知らない。つん堂さんと私たちが同姓だということを知ったのは、メールアドレスをお聞きしてからだ。日本ではベスト3に入るありふれた姓だから奇遇ということもないが。
つん堂さんの蒐集した蔵書を私どもの店に置かせていただくようになったのは、上記のように古本という共通の話題から親しくなったということもあるが、何よりもつん堂さんも書かれているように「好みが一致」しているからだ。
贅沢を言うようだが、私たちは嫌な本は店に置きたくないと思っている。新刊書店ではそうはいかないが、古本屋だからこそできる贅沢なのである。つん堂文庫は 長野の私たちにとって、東京からの風のように感じている。現に「ウェッジ文庫」のことは全く知らなかった。不勉強ではあるのだが。
つん堂さんにとっては、長野の片隅の古本屋に自身の蒐集本を並べても、その反響は無いに等しいものなのだとは思うが、長野の古本屋の応援団長になってしまった因果と諦めてください。
さて、そこでも述べたつん堂文庫のこと。それほど大げさなものではなく、長野の古本市で残った本をお預かりしたということ、せっかくだからそれを店に並べましょうということになったという次第なのである。自分の集めた本の反応を見たいというつん堂さんの希望もあった。
私どもとしても、つん堂さんの選んだ本ならぜひ置かせていただきたいということで、つん堂文庫開設の運びとなったものである。大書店の丸善と光風舎を比較したのでは気がひけるのだが、松丸本舗のようなものを実はイメージしているのである。
愛書家のつん堂さんのことについては、ここでいろいろ説明するよりはご自身のブログを見ていただくのがいいと思う。光風舎との縁は、古本屋ツアーさんの記事に興味を覚え、訪れたこの店が気に入っていただいたということからだと思う。最初の印象をつん堂さんのブログから引用すると、
「店内もしんしんとして、じっくり本を選ぶにはつらい。
ただし、店内はきれいに整理され、良書がぎっしりとうれしい状況。だけど、だけど、うまくはいきません。まず、好みが一致しすぎて、所持本とカブリがほとんど。しかも、値段はしっかりついている。こうなるとなかなか手が伸びないものです。」(1月13日付)
その後、仕事の関係で長野出張の多いつん堂さんは、時々光風舎に来ていただくようになった。つん堂さんは親切な方で、東京の古本事情に疎い私たちにいろいろと話してくださり、先月の「あいおい古本まつり」では東京の愛書家の方たちをご紹介いただき、ご一緒に食事をさせていただいた。
ただ、あくまでも客と店主という関係だからお互いプライベートなことは知らない。つん堂さんと私たちが同姓だということを知ったのは、メールアドレスをお聞きしてからだ。日本ではベスト3に入るありふれた姓だから奇遇ということもないが。
つん堂さんの蒐集した蔵書を私どもの店に置かせていただくようになったのは、上記のように古本という共通の話題から親しくなったということもあるが、何よりもつん堂さんも書かれているように「好みが一致」しているからだ。
贅沢を言うようだが、私たちは嫌な本は店に置きたくないと思っている。新刊書店ではそうはいかないが、古本屋だからこそできる贅沢なのである。つん堂文庫は 長野の私たちにとって、東京からの風のように感じている。現に「ウェッジ文庫」のことは全く知らなかった。不勉強ではあるのだが。
つん堂さんにとっては、長野の片隅の古本屋に自身の蒐集本を並べても、その反響は無いに等しいものなのだとは思うが、長野の古本屋の応援団長になってしまった因果と諦めてください。
2011年09月26日
薄幸の作家、小山清
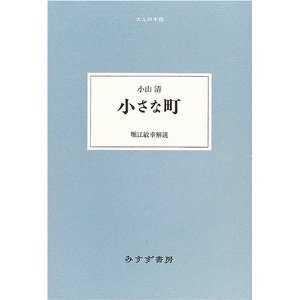 昨日は、12時半頃に店を開けて、15時半頃に店番を代わってもらったのだが、その間来店客は1組、売り上げはゼロという惨憺たる状態であった。こんな日がひと月に何度かはある。
昨日は、12時半頃に店を開けて、15時半頃に店番を代わってもらったのだが、その間来店客は1組、売り上げはゼロという惨憺たる状態であった。こんな日がひと月に何度かはある。ジェットコースターに乗っているような売り上げの上がり下がりは、もうすっかり慣れてしまったが、そうは言ってもそのいちいちに反応して、喜んだり嘆いたりするのは、我ながら情けない。
こんな日は開き直ってと、今度当店に設けることになったつん堂文庫から1冊を抜き出して読みはじめた。 つん堂文庫については改めて書くことにしよう。
小山清「小さな町」みすず書房
この作家には思い出がある。20歳ころに憧れていた女性が小山清が好きだと言っていたので、私もいくつかの短編を読んだことがあったのだ。 どんな本でどんな内容だったのか、もうすっかり忘れていた。
「 小さな町」は読んだことがなかった。かつて新聞配達をしていた町の思い出を綴ったものだ。この町は東京大空襲で焼け、そこに住む人々も散り散りになってしまった。ただ、作者はそのことについては強く言及していない。そこに住んだ人たちとの思い出を愛惜を込めてたんたんと描いている。
この作家の作品がいま、多くの読者を獲得しているのだという。上記のみすず書房の本も最近になって出版されたものである。小山清に限らず、いま、私小説といわれる昔の地味な作家の作品がよく読まれているということを聞いた。私は小説の類はほとんど読まないので、そのへんのことはよくわからないのだが、商売柄地味な作家の本に法外な古書価格がついていてびっくりすることがある。
貧しいが慎ましやかに暮らす人々に共感して小説を書いた作家がいて、その作家の作品に共鳴する熱心な読者がいる、こういう構図は罪がないといえばその通りなのだが、ちょっとこれでは寂しいのでは。もっと型破りの作家に人気が集まってもいいような気がする。
2011年09月25日
一転、一箱古本市参加者の弁明。
遊歴書房が主催した一箱古本市も盛況のうちに終わり、私も大いに楽しませていただいたのだが、出ない宣言をしておきながら出店してしまったという、格好悪さがあった。
古本市が終わって、もう開催の邪魔ということにはならないと思うので、書くべきことは書いておこうと思う。来年も一箱ということを考えているのなら、多少は参考になろう。
昨日、店に北島書店さんが見えた。昨日の古本市のことが気になってということであった。昨日も書いたように北島さんはこの辺の古本屋の中では一番のベテランである。盛況であった旨をお伝えしたら、それはよかったと喜んでおられた。スタンプラリーの効果か北島さんの店にも、普段来ない若い女性が何人も来られたという。光風舎にも地図を持って来店された方が数名いたと共同経営者が話していた。
売り上げには繋がらなかったにしても、普段入りにくいウチの店や北島さんの店に入っていただいただけでも今後につながる効果である。古本屋地図を作ってくれた遊歴さんには大いに感謝しなければならない。スタンプラリーをやるかどうかは別として、この地図は毎年改訂していきたいねと北島さんと話した。
もう一つ、北島さんと私たちの意見が一致したのは、来年以降も続けるなら遊歴書房単独の主催では続かないだろうということだった。実行委員会方式にすべきだろうというのである。私が最初不参加を決めたのは、遊歴書房の単独主催であることと、会場として彼がカネマツの倉庫にこだわったからだ。
遊歴書房さんにしてみれば、時間ばかりかかって前へ進まないような話し合いを重ねるよりは、自分が突っ走って、続きたいものはついてくればいいという考えであったのだろう。結果はその通りになって、あとから8軒の店がついて行くという形になった。しかし、これでは資金的にも感情的にも長続きしないのではないか。時間をかけても話し合いをし、それでも一緒にやりたくない人ははずれればいいのだ。
そんなことにこだわるのは、私のかねてからの持論なのだが、長野の古本屋が1軒の大きな古本屋のように機能するということが共存の鍵であると思うからだ。これは各書店にとってということではない。あくまでも読者にとってそのように見えればいいということである。
古本好きは欲張りである。長野の古本屋のどこも1軒では彼らの欲望を満たすことはできない。それが今回の地図のように12軒もあるのだということになると、場合によっては遠方からでも行ってみようかという人も現れるかもしれない。 12軒全てを回ってもらうということは無理かも知れないが、若い女性なら、チャンネルとひふみよと行って、もしかしたら間違えて光風舎にも来るかも知れない。場違いと思っても、たまたまタルホを買ってしまうかも知れない。ありがたいことである。
だから、年に1度のお祭り(古本市)ならば皆でズクを出し、お金を出して盛り上げようではないかと、私は思うのである。南陀楼さんが谷根千で一箱をやりたいと思ったのも、おそらくは谷根千という魅力的な地域の中に古本市を溶けこませたいという思いがあったからだと思う。トークの中でも、今後の長野の古本市の課題として、何カ所かを回遊することを提案しておられた。
せっかく遊歴書房さんが火をつけてくれた祭りである。絶やさないようにしたいと思う。昨日、北島さんは春にももう一回やってもおもしろいんじゃないかとも言っておられた。ぜひそうしましょう。
古本市が終わって、もう開催の邪魔ということにはならないと思うので、書くべきことは書いておこうと思う。来年も一箱ということを考えているのなら、多少は参考になろう。
昨日、店に北島書店さんが見えた。昨日の古本市のことが気になってということであった。昨日も書いたように北島さんはこの辺の古本屋の中では一番のベテランである。盛況であった旨をお伝えしたら、それはよかったと喜んでおられた。スタンプラリーの効果か北島さんの店にも、普段来ない若い女性が何人も来られたという。光風舎にも地図を持って来店された方が数名いたと共同経営者が話していた。
売り上げには繋がらなかったにしても、普段入りにくいウチの店や北島さんの店に入っていただいただけでも今後につながる効果である。古本屋地図を作ってくれた遊歴さんには大いに感謝しなければならない。スタンプラリーをやるかどうかは別として、この地図は毎年改訂していきたいねと北島さんと話した。
もう一つ、北島さんと私たちの意見が一致したのは、来年以降も続けるなら遊歴書房単独の主催では続かないだろうということだった。実行委員会方式にすべきだろうというのである。私が最初不参加を決めたのは、遊歴書房の単独主催であることと、会場として彼がカネマツの倉庫にこだわったからだ。
遊歴書房さんにしてみれば、時間ばかりかかって前へ進まないような話し合いを重ねるよりは、自分が突っ走って、続きたいものはついてくればいいという考えであったのだろう。結果はその通りになって、あとから8軒の店がついて行くという形になった。しかし、これでは資金的にも感情的にも長続きしないのではないか。時間をかけても話し合いをし、それでも一緒にやりたくない人ははずれればいいのだ。
そんなことにこだわるのは、私のかねてからの持論なのだが、長野の古本屋が1軒の大きな古本屋のように機能するということが共存の鍵であると思うからだ。これは各書店にとってということではない。あくまでも読者にとってそのように見えればいいということである。
古本好きは欲張りである。長野の古本屋のどこも1軒では彼らの欲望を満たすことはできない。それが今回の地図のように12軒もあるのだということになると、場合によっては遠方からでも行ってみようかという人も現れるかもしれない。 12軒全てを回ってもらうということは無理かも知れないが、若い女性なら、チャンネルとひふみよと行って、もしかしたら間違えて光風舎にも来るかも知れない。場違いと思っても、たまたまタルホを買ってしまうかも知れない。ありがたいことである。
だから、年に1度のお祭り(古本市)ならば皆でズクを出し、お金を出して盛り上げようではないかと、私は思うのである。南陀楼さんが谷根千で一箱をやりたいと思ったのも、おそらくは谷根千という魅力的な地域の中に古本市を溶けこませたいという思いがあったからだと思う。トークの中でも、今後の長野の古本市の課題として、何カ所かを回遊することを提案しておられた。
せっかく遊歴書房さんが火をつけてくれた祭りである。絶やさないようにしたいと思う。昨日、北島さんは春にももう一回やってもおもしろいんじゃないかとも言っておられた。ぜひそうしましょう。
2011年09月24日
長野の一箱古本市
古本屋だけでは食えない南宜堂は、夜中に働くしかない。1時から2時間だけの仮眠の後働き、カネマツで開かれる一箱古本市へ。つん堂さんとの約束の時間に15分遅刻してしまった。
全部で21の箱が集まった会場で、11時から古本市が始まった。南宜堂の箱はあちらこちらのアドバイスをみんな聞き入れたためぐじゃぐじゃ、いったい何を売りたいのかサッパリわからなくなってしまった。その中で、一番売れたのが、10年ほど前に私が復刻して売り出したものの、あまり売れなくてデッドストックになっていた大正14年の北信地区の主な町の市街地図。おまけにやはり昔出版したもののまったく売れず、出版社光風舎を潰す元凶となった長野市中央通りの昭和初期の写真集も売れて、10年前にこれだけ売れていたら光風舎ビルが建っていたのにと思うが後の祭。
祭といえば、一箱は祭だ、高遠で長藤 文庫をやっていたOさんや会津でお会いしたじんた堂さんも見えて懐かしくも楽しい時間が過ごせた。一箱古本市の模様は隣に店を出されていたつん堂さんや主催者の遊歴さんがブログでアップされると思う。
ゲストの南陀楼綾繁さんは一箱の合間を縫って、長野の古本屋を精力的にまわられたようだ。古本市の後のトークでそんなお話があった。特に印象に残った店として、北島書店、山崎書店、荻原書店の名前をあげられていた。荻原は新刊書店だが、あとの2店はいずれも長野では老舗の古本屋で、私がいうところの長野の古本屋第2世代の人たちだ。
南陀楼さんの目に止まったのは、それらの店頭にある黒めの本たち。場合によっては100年近くも前に出版されて、古本屋の本棚に埋もれていた本を見つけ出す楽しみは、歴史を積んだ古本屋をまわらなければ味わえないものなのだろう。今風の流行を追いかけた古本屋全盛の昨今の状況への南陀楼さんの警鐘と聞いた。
確かに長野の古本屋の中では、上記の店に加えて新井大正堂あたりがプロフェッショナルで、あとの古本屋はアマチュアなのかもしれない。棚の持つ時代の厚みと言ったらいいのだろうか。あの魅力は古本屋を何十年もやらなければ出せないものなのかもしれない。
上で紹介した昔の長野の写真集の原本は北島書店で購入したものだ。大正13年に中央通りの拡幅工事が完成したのを記念して作られた写真集で、コロタイプ印刷の贅沢なものだった。私はこの本の美しさと被写体となった長野の商家のたたずまいに惹かれて復刻を決意した。こいう出会いは老舗の古本屋の棚だからこそ味わえるものだ。
一箱古本市を提唱し、新しい古本の動きをリードしている南陀楼さんの口からこういう話を聞けるというのは意外であった。でも黒目の棚から面白い本を見つけ出すということが広がっていったなら、これはこれで古本の世界の幅が広がるというもので歓迎すべきことだろう。まあ、こういうことは一昔前の古本好きがみんなやっていたことなんだが、稲垣足穂がいまの若者に新鮮なように、若い古本好きには新鮮に映るのかもしれない。
長野のみなさん、老舗の古本屋を訪ねましょう。
続きを読む
全部で21の箱が集まった会場で、11時から古本市が始まった。南宜堂の箱はあちらこちらのアドバイスをみんな聞き入れたためぐじゃぐじゃ、いったい何を売りたいのかサッパリわからなくなってしまった。その中で、一番売れたのが、10年ほど前に私が復刻して売り出したものの、あまり売れなくてデッドストックになっていた大正14年の北信地区の主な町の市街地図。おまけにやはり昔出版したもののまったく売れず、出版社光風舎を潰す元凶となった長野市中央通りの昭和初期の写真集も売れて、10年前にこれだけ売れていたら光風舎ビルが建っていたのにと思うが後の祭。
祭といえば、一箱は祭だ、高遠で長藤 文庫をやっていたOさんや会津でお会いしたじんた堂さんも見えて懐かしくも楽しい時間が過ごせた。一箱古本市の模様は隣に店を出されていたつん堂さんや主催者の遊歴さんがブログでアップされると思う。
ゲストの南陀楼綾繁さんは一箱の合間を縫って、長野の古本屋を精力的にまわられたようだ。古本市の後のトークでそんなお話があった。特に印象に残った店として、北島書店、山崎書店、荻原書店の名前をあげられていた。荻原は新刊書店だが、あとの2店はいずれも長野では老舗の古本屋で、私がいうところの長野の古本屋第2世代の人たちだ。
南陀楼さんの目に止まったのは、それらの店頭にある黒めの本たち。場合によっては100年近くも前に出版されて、古本屋の本棚に埋もれていた本を見つけ出す楽しみは、歴史を積んだ古本屋をまわらなければ味わえないものなのだろう。今風の流行を追いかけた古本屋全盛の昨今の状況への南陀楼さんの警鐘と聞いた。
確かに長野の古本屋の中では、上記の店に加えて新井大正堂あたりがプロフェッショナルで、あとの古本屋はアマチュアなのかもしれない。棚の持つ時代の厚みと言ったらいいのだろうか。あの魅力は古本屋を何十年もやらなければ出せないものなのかもしれない。
上で紹介した昔の長野の写真集の原本は北島書店で購入したものだ。大正13年に中央通りの拡幅工事が完成したのを記念して作られた写真集で、コロタイプ印刷の贅沢なものだった。私はこの本の美しさと被写体となった長野の商家のたたずまいに惹かれて復刻を決意した。こいう出会いは老舗の古本屋の棚だからこそ味わえるものだ。
一箱古本市を提唱し、新しい古本の動きをリードしている南陀楼さんの口からこういう話を聞けるというのは意外であった。でも黒目の棚から面白い本を見つけ出すということが広がっていったなら、これはこれで古本の世界の幅が広がるというもので歓迎すべきことだろう。まあ、こういうことは一昔前の古本好きがみんなやっていたことなんだが、稲垣足穂がいまの若者に新鮮なように、若い古本好きには新鮮に映るのかもしれない。
長野のみなさん、老舗の古本屋を訪ねましょう。
続きを読む





