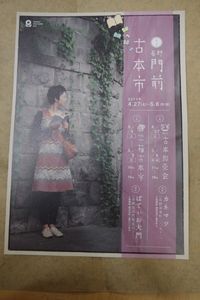2012年10月09日
会津の一箱古本市
連休中の7日、8日の二日間会津で一箱古本市に参加してきた。信州では軽井沢町で追分コロニーさんの「ホンモノ市」が同じ時期に開催されていて、こちらにもぜひ出かけたかったのであるが、会津旅行は夏から決まっていた行事であったので、追分行きは断念した次第。
前からの行事をキャンセルしての一箱出店は、歴史仲間のみなさんにたいへんご迷惑をおかけしてしたが、枯れ木も山の賑わいで会津の古本市の盛り上げのお手伝いがしたくてわがままを言ってしまった。夜の懇親会には何とか間に合ったのだが、申し訳ないことをしてしまいました。
7日は会津若松で、紀州屋1934という昭和初期の古いモルタル作りの建物の前に店を出させていただいた。しかも、並べた本の後ろには古いボンネットバスがどんと構えていた。売り上げは振るわなかったが、高遠で感じたような後味の悪さはなかった。スタッフの人たちが何とか盛り上げようと頑張っている姿を見たからだと思う。東京から著名なゲストが来たわけではないし、お客さんも地元の人が中心で、地味ではあったがいい古本市だったと思う。

翌日は喜多方の「つきとおひさま」という食堂で、こちらもこじんまりとした古本市だった。出店者が5店だけということもあって、下は20代の青年から上は私まで、男女もさまざまであったが、和気藹々とした雰囲気の中で古本市をすることができた。

会場の食堂を経営するご夫婦は、ご主人が長州出身、奥様が会津出身というカップルで、「明治の兄弟」の現代版のような葛藤があったのかどうかは知らないが、現在は二人とも喜多方の地に溶け込んでいるようである。料理も工夫が凝らされていて美味しく、常連のお客さんがたくさん来ておられた。その人たちが帰りがけに古本を買っていただいたので結構な売り上げとなった。売り上げトップという「Book Book Aizu賞」なるものをいただいた。

いま、地方の一箱古本市は運営が難しくなったと聞いている。出店者が集まらないとか、お客さんがこないとか、運営スタッフがいないとか、いろいろとマイナスな話が伝わってくる。しかし、そんなないないづくしであっても、少数の出店で、売り上げも期待しないで、一日を古本談義に楽しく過ごせたらそれでいいか、そんな気持ちでやってみれば長続きするのかもしれないなと思ったのである。それで、会津で来年も古本市が開かれるなら、老骨にむち打っても参加したいなというのが二日間の感想である。
前からの行事をキャンセルしての一箱出店は、歴史仲間のみなさんにたいへんご迷惑をおかけしてしたが、枯れ木も山の賑わいで会津の古本市の盛り上げのお手伝いがしたくてわがままを言ってしまった。夜の懇親会には何とか間に合ったのだが、申し訳ないことをしてしまいました。
7日は会津若松で、紀州屋1934という昭和初期の古いモルタル作りの建物の前に店を出させていただいた。しかも、並べた本の後ろには古いボンネットバスがどんと構えていた。売り上げは振るわなかったが、高遠で感じたような後味の悪さはなかった。スタッフの人たちが何とか盛り上げようと頑張っている姿を見たからだと思う。東京から著名なゲストが来たわけではないし、お客さんも地元の人が中心で、地味ではあったがいい古本市だったと思う。

翌日は喜多方の「つきとおひさま」という食堂で、こちらもこじんまりとした古本市だった。出店者が5店だけということもあって、下は20代の青年から上は私まで、男女もさまざまであったが、和気藹々とした雰囲気の中で古本市をすることができた。

会場の食堂を経営するご夫婦は、ご主人が長州出身、奥様が会津出身というカップルで、「明治の兄弟」の現代版のような葛藤があったのかどうかは知らないが、現在は二人とも喜多方の地に溶け込んでいるようである。料理も工夫が凝らされていて美味しく、常連のお客さんがたくさん来ておられた。その人たちが帰りがけに古本を買っていただいたので結構な売り上げとなった。売り上げトップという「Book Book Aizu賞」なるものをいただいた。

いま、地方の一箱古本市は運営が難しくなったと聞いている。出店者が集まらないとか、お客さんがこないとか、運営スタッフがいないとか、いろいろとマイナスな話が伝わってくる。しかし、そんなないないづくしであっても、少数の出店で、売り上げも期待しないで、一日を古本談義に楽しく過ごせたらそれでいいか、そんな気持ちでやってみれば長続きするのかもしれないなと思ったのである。それで、会津で来年も古本市が開かれるなら、老骨にむち打っても参加したいなというのが二日間の感想である。
Posted by 南宜堂 at 22:33│Comments(0)
│古本屋の日々