2012年08月28日
殿様の度量
一代の君あれば、又一代の臣下あり。
松代藩家老恩田木工の事績を記した「日暮硯」の中の一節です。今度の本の帯に使っています。この藩史シリーズは、帯にその藩を象徴するような名言を載せるのだそうで、この言葉がえらばれました。出版社のスタッフの皆さんとの話で、今風ではありませんね、というようなことになったのですが、今の世の中、あまり上下関係を言わなくなりました。親と子、先生と生徒、上司と部下、友だちのような関係がいいのだとされるのが今風のようです。
一代の君とは、松代藩第六代藩主真田幸弘のことです。この人はわずか十三歳で藩主の座についています。その聡明さを語るエピソードとして、鳥籠の話が冒頭にあるのです。
幸弘14、5歳のこととされるこの話は次のようなものです。
ある日、家来の一人が気晴らしに鳥を飼うことをすすめます。幸弘はそれでは万事任せるから立派な鳥籠を作るようにと家来に命じます。出来上がった鳥籠を前に、幸弘はちょっとそこに入ってみないかと家来に言います。やがて煙草やらお茶やら菓子やら、食事までが運ばれ、お前はずっとそこで暮らすがよいと家来に命じます。これには家来も驚いて、それだけはご勘弁をと泣いて懇願します。
そんな家来に、鳥の自由を奪うことの愚を説くわけですが、その時言葉で言って聞かせずに、鳥籠に飼われることの苦しさを身をもって体験させるのです。
実際にそんなことがあったのかはわかりません。奈良本辰也さんは似たようなことがあったのだろうとしていますが、松代藩で鳥を飼うという習慣がなくなったという話も聞きません。それに、このエピソードは有名な「徒然草」にあるのです。「日暮硯」の著者は吉田兼好が好きだったらしく、タイトルからして「日暮らし硯に向かいて」からとっているようです。この辺に「日暮硯」の作者を探る鍵があるような気もします。
それはともかく、こんな賢君がいたのだから、その君に見出されて恩田木工のような人が活躍できたのだろうというわけです。
現代書館の編集の方は、「上のものが範を垂れ、下のものが見習う」というように解釈されていますが、私は木工に自由に藩政をやらせた度量こそが幸弘の賢君たる所以ではないかと思っています。「やってみなはれ」の精神です。
松代藩家老恩田木工の事績を記した「日暮硯」の中の一節です。今度の本の帯に使っています。この藩史シリーズは、帯にその藩を象徴するような名言を載せるのだそうで、この言葉がえらばれました。出版社のスタッフの皆さんとの話で、今風ではありませんね、というようなことになったのですが、今の世の中、あまり上下関係を言わなくなりました。親と子、先生と生徒、上司と部下、友だちのような関係がいいのだとされるのが今風のようです。
一代の君とは、松代藩第六代藩主真田幸弘のことです。この人はわずか十三歳で藩主の座についています。その聡明さを語るエピソードとして、鳥籠の話が冒頭にあるのです。
幸弘14、5歳のこととされるこの話は次のようなものです。
ある日、家来の一人が気晴らしに鳥を飼うことをすすめます。幸弘はそれでは万事任せるから立派な鳥籠を作るようにと家来に命じます。出来上がった鳥籠を前に、幸弘はちょっとそこに入ってみないかと家来に言います。やがて煙草やらお茶やら菓子やら、食事までが運ばれ、お前はずっとそこで暮らすがよいと家来に命じます。これには家来も驚いて、それだけはご勘弁をと泣いて懇願します。
そんな家来に、鳥の自由を奪うことの愚を説くわけですが、その時言葉で言って聞かせずに、鳥籠に飼われることの苦しさを身をもって体験させるのです。
実際にそんなことがあったのかはわかりません。奈良本辰也さんは似たようなことがあったのだろうとしていますが、松代藩で鳥を飼うという習慣がなくなったという話も聞きません。それに、このエピソードは有名な「徒然草」にあるのです。「日暮硯」の著者は吉田兼好が好きだったらしく、タイトルからして「日暮らし硯に向かいて」からとっているようです。この辺に「日暮硯」の作者を探る鍵があるような気もします。
それはともかく、こんな賢君がいたのだから、その君に見出されて恩田木工のような人が活躍できたのだろうというわけです。
現代書館の編集の方は、「上のものが範を垂れ、下のものが見習う」というように解釈されていますが、私は木工に自由に藩政をやらせた度量こそが幸弘の賢君たる所以ではないかと思っています。「やってみなはれ」の精神です。
Posted by 南宜堂 at 14:06│Comments(0)
│松代



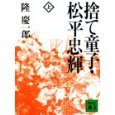





書き込まれた内容は公開され、ブログの持ち主だけが削除できます。