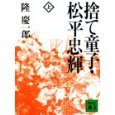2010年05月01日
象山紀行 9
佐久間象山が、江戸木挽町で砲術及び経書の塾を開いたのは、嘉永四年のことである。「鬢髮(びんぱつ)蓬の如く、癯骨(くこつ)衣に勝(た)えざるが如く」の吉田寅次郎が入門したのもこのときであった。
木挽町という地名は現在の地図にはない。井出孫六氏の『小説佐久間象山」に「(狩野)勝川塾とま向いに佐久間象山の家があった。」とあるので、手もとにある江戸切絵図を開いてみた。この切絵図は、安政四丁巳歳改の尾張屋版であるので残念ながら象山の家はない。嘉永7年、吉田寅次郎の下田踏海事件に連座して、国元蟄居を申し付けられ、安政元年に松代に帰っているからだ。
幸いなことに狩野勝川の塾は切絵図にあった。現在の地図と照合してみると、銀座5丁目の松坂屋の角から築地方面にみゆき通りを来ると左手に時事通信社のビルがある。このあたりが勝川の塾があった場所である。象山の塾があったのは、みゆき通りを挟んだ向かいということになる。
象山が本格的に蘭学を学びはじめたのは、弘化元年34歳の時といわれている。坪井信道の弟子である黒川良安についてオランダ語を学びはじめたのである。このとき黒川との間でかわしたのが、黒川にオランダ語を教えてもらうかわりに、象山が黒川に漢学を教えるというものであった。
オランダ語をマスターした象山は、兵書、砲術書そして自然科学書と次々に渉猟し、それを自分のものにしていった。
嘉永4年に木挽町で塾を開く頃には西洋砲術の大家として、象山は広くその名声は知られるようになっていた。

木挽町という地名は現在の地図にはない。井出孫六氏の『小説佐久間象山」に「(狩野)勝川塾とま向いに佐久間象山の家があった。」とあるので、手もとにある江戸切絵図を開いてみた。この切絵図は、安政四丁巳歳改の尾張屋版であるので残念ながら象山の家はない。嘉永7年、吉田寅次郎の下田踏海事件に連座して、国元蟄居を申し付けられ、安政元年に松代に帰っているからだ。
幸いなことに狩野勝川の塾は切絵図にあった。現在の地図と照合してみると、銀座5丁目の松坂屋の角から築地方面にみゆき通りを来ると左手に時事通信社のビルがある。このあたりが勝川の塾があった場所である。象山の塾があったのは、みゆき通りを挟んだ向かいということになる。
象山が本格的に蘭学を学びはじめたのは、弘化元年34歳の時といわれている。坪井信道の弟子である黒川良安についてオランダ語を学びはじめたのである。このとき黒川との間でかわしたのが、黒川にオランダ語を教えてもらうかわりに、象山が黒川に漢学を教えるというものであった。
オランダ語をマスターした象山は、兵書、砲術書そして自然科学書と次々に渉猟し、それを自分のものにしていった。
嘉永4年に木挽町で塾を開く頃には西洋砲術の大家として、象山は広くその名声は知られるようになっていた。

Posted by 南宜堂 at 21:22│Comments(0)
│松代
※このブログではブログの持ち主が承認した後、コメントが反映される設定です。