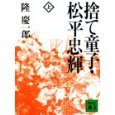2013年04月02日
象山先生
遠来の客人Fさんを案内して松代に行ってきた。昨年のクリスマスイブに松代テレビに出させていただいて以来だから3ヶ月ぶりの松代である。
今松代は佐久間象山が注目されている。あちらこちらに象山の展示があった。大河ドラマの影響だ。奥田瑛二の名演もあって、訪れる人も多いようだ。Fさんは会津生まれで会津若松に住んでいる。「八重の桜」も見ているそうで、会津では佐久間象山というより奥田瑛二で通っているそうだ。あの世の象山これには苦笑いだろう。地元松代ではぞうざんせんせーと呼ばれているのをFさんは盛んに感心していた。会津で先生と呼ばれるのは強いていえば野口英世くらいだと。
地元松代でなくとも長野県歌「信濃国」には「ぞうざんさくませんせーも」とあるから、信州のこどもはみな佐久間象山の名前は知っている。しかしこの人がどんなことをした偉人なのか、よくはわからないのではないか。私は大人だがいまだにその偉大さをよく理解できていないように思う。
弟子の吉田松陰は、師象山について次のように述べている。「象山高く突兀(とっこつ)たり、雲翳(うんえい)仰ぐべきこと難し。何れの日にか天風起り、快望せん狻猊の蟠まるを」。松代にある象山(ぞうざん)は小山のようなものだが、松陰が見た佐久間象山は仰ぎ見るような存在であったのだろう。象山は学問を身につけるだけではもの足らず、実際の行動によって理想を実現することを弟子に求め、自らもそれを実践した。松陰に海外への渡航を勧めたのは象山であったし、書物から得た知識で大砲も電信機も作ってみた。
罪を許されて上洛した後も、自らの信ずる道に従って公武合体を進め、天皇を江戸に遷そうとさえ考えていたようだ。象山にとって公武合体は方法であった。外国の脅威が迫る中、尊皇派と佐幕派が全面的に戦うことを避けるための方法論であったようだ。
象山が暗殺された数年後、土佐の坂本龍馬が大政奉還を画策したのも象山と同じ発想から生まれた方法論であったようだ。内戦を避けるための大政奉還も薩長に倒幕の口実とされ、龍馬は暗殺されてしまう。タイプは違うが、象山も龍馬も内戦を避けるために行動したという点では共通項があるのではないか。
象山の弟子であり義兄である勝海舟は、明治になっての象山評で「佐久間象山は、もの知りだったよ。学問も博し、見識も多少もっていたよ。しかしどうもほら吹きでこまるよ。」と述べているが、海舟にとっては象山の実践論は詰めが甘い「ほら」に思えたのだろう。実践面では弟子海舟が一枚上であるようだ。
今松代は佐久間象山が注目されている。あちらこちらに象山の展示があった。大河ドラマの影響だ。奥田瑛二の名演もあって、訪れる人も多いようだ。Fさんは会津生まれで会津若松に住んでいる。「八重の桜」も見ているそうで、会津では佐久間象山というより奥田瑛二で通っているそうだ。あの世の象山これには苦笑いだろう。地元松代ではぞうざんせんせーと呼ばれているのをFさんは盛んに感心していた。会津で先生と呼ばれるのは強いていえば野口英世くらいだと。
地元松代でなくとも長野県歌「信濃国」には「ぞうざんさくませんせーも」とあるから、信州のこどもはみな佐久間象山の名前は知っている。しかしこの人がどんなことをした偉人なのか、よくはわからないのではないか。私は大人だがいまだにその偉大さをよく理解できていないように思う。
弟子の吉田松陰は、師象山について次のように述べている。「象山高く突兀(とっこつ)たり、雲翳(うんえい)仰ぐべきこと難し。何れの日にか天風起り、快望せん狻猊の蟠まるを」。松代にある象山(ぞうざん)は小山のようなものだが、松陰が見た佐久間象山は仰ぎ見るような存在であったのだろう。象山は学問を身につけるだけではもの足らず、実際の行動によって理想を実現することを弟子に求め、自らもそれを実践した。松陰に海外への渡航を勧めたのは象山であったし、書物から得た知識で大砲も電信機も作ってみた。
罪を許されて上洛した後も、自らの信ずる道に従って公武合体を進め、天皇を江戸に遷そうとさえ考えていたようだ。象山にとって公武合体は方法であった。外国の脅威が迫る中、尊皇派と佐幕派が全面的に戦うことを避けるための方法論であったようだ。
象山が暗殺された数年後、土佐の坂本龍馬が大政奉還を画策したのも象山と同じ発想から生まれた方法論であったようだ。内戦を避けるための大政奉還も薩長に倒幕の口実とされ、龍馬は暗殺されてしまう。タイプは違うが、象山も龍馬も内戦を避けるために行動したという点では共通項があるのではないか。
象山の弟子であり義兄である勝海舟は、明治になっての象山評で「佐久間象山は、もの知りだったよ。学問も博し、見識も多少もっていたよ。しかしどうもほら吹きでこまるよ。」と述べているが、海舟にとっては象山の実践論は詰めが甘い「ほら」に思えたのだろう。実践面では弟子海舟が一枚上であるようだ。

Posted by 南宜堂 at 08:23│Comments(0)
│松代