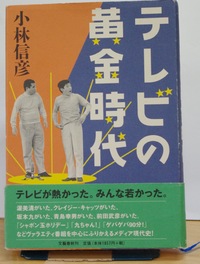2013年06月30日
薮の中
平安堂長野店のカフェゼミナールで1時間半ほどお話をさせていただいた。最近はすっかり真田と松代が持ちネタになってしまったようで、「真田一族と松代藩」の話を。とりとめもなく話してしまったようなのだが、実は密かに自分の中ではテーマを決めていたのだ。それがすなわち「薮の中」なのである。
江戸時代に作られた真田ものなのだが、大きく2つのものがある。元禄時代に書かれた実録小説といわれる「真田三代記」の系統と、松代藩内で書かれたいわゆる歴史書「滋野世記」とか「真武内伝」とかいわれるものの類いである。
真田氏のルーツについては、両者とも清和天皇の末裔であるということで共通しているのだが、信之の扱い、家康についての見解、幸村のことと全く別のとらえ方をしているのである。
「滋野世紀」に収録されている「上田軍記」は第一次・第二次上田合戦を中心に描いたものだが、この主人公は昌幸と嫡男の信之である。そしておもしろいと思ったのは、徳川方にも相応の活躍の場が与えられているのである。
さらには関ヶ原後の真田仕置きについても、昌幸・信之・家康三者それぞれに華を持たせたような記述になっているのである。籠城し最後の一兵まで戦おうという昌幸。このまま真田を亡ぼすのは惜しいという家康。そして、報賞はいらないからどうか父と弟の命を助けてほしいという信之、誰もがいい役割を与えられている。おそらくこれは、松代藩としての気遣いであろうと思う。信之については藩祖であるので当然のこと、その父親である昌幸にも十分の評価が与えられている。家康については真田ものでは悪人なのだが、松代藩としては東照権現を悪者にするわけにはいかない。
これに対して「真田三代記」は家康を徹底的に悪人にしている。また、信之についてはほとんど言及がないのである。大坂で作られた地下出版のようなものだから好きに書けたのであろう。それと太閤びいきの大坂の人々は家康嫌いのだ。読者の反応に敏感だったのだ。幸村が無敵の英雄のように描かれるのもそんな理由からなのかもしれない。
歴史は権力者の都合のいいように書かれるというが、その通りだと思う。明治維新についても然り、太平洋戦争についても安倍政権が続くと現在とは逆の見方が出てくるのだろう。江戸時代は徳川の絶対政権であったので、幸村は非合法な出版でしか活躍の場を与えられなかった。しかし、江戸時代も後半になると「敵ながらあっぱれ」的な視点で幸村も復権してきた。松代藩内でも幸村顕彰の動きは江戸時代からあったようだ。
最近芥川龍之介の「薮の中」を読み直してみた。以前読んだ時の印象で、ものの見方は人によって違う。ずいぶん曖昧なものだということがその内容だと思っていたのだが、そういうことではないようだ。男が死んで女が生き残ったという事実があって、それぞれのモノローグを綴りあわせたような短編小説だが、その言っていることがそれぞれに違う。男は自分が殺したというもの、自殺なのだというもの、それが語るものの立場や都合によって微妙に違う。
真田幸村に評価にしても、いろいろな人に語らせればその都度違う。真実は一つではないのだ。
江戸時代に作られた真田ものなのだが、大きく2つのものがある。元禄時代に書かれた実録小説といわれる「真田三代記」の系統と、松代藩内で書かれたいわゆる歴史書「滋野世記」とか「真武内伝」とかいわれるものの類いである。
真田氏のルーツについては、両者とも清和天皇の末裔であるということで共通しているのだが、信之の扱い、家康についての見解、幸村のことと全く別のとらえ方をしているのである。
「滋野世紀」に収録されている「上田軍記」は第一次・第二次上田合戦を中心に描いたものだが、この主人公は昌幸と嫡男の信之である。そしておもしろいと思ったのは、徳川方にも相応の活躍の場が与えられているのである。
さらには関ヶ原後の真田仕置きについても、昌幸・信之・家康三者それぞれに華を持たせたような記述になっているのである。籠城し最後の一兵まで戦おうという昌幸。このまま真田を亡ぼすのは惜しいという家康。そして、報賞はいらないからどうか父と弟の命を助けてほしいという信之、誰もがいい役割を与えられている。おそらくこれは、松代藩としての気遣いであろうと思う。信之については藩祖であるので当然のこと、その父親である昌幸にも十分の評価が与えられている。家康については真田ものでは悪人なのだが、松代藩としては東照権現を悪者にするわけにはいかない。
これに対して「真田三代記」は家康を徹底的に悪人にしている。また、信之についてはほとんど言及がないのである。大坂で作られた地下出版のようなものだから好きに書けたのであろう。それと太閤びいきの大坂の人々は家康嫌いのだ。読者の反応に敏感だったのだ。幸村が無敵の英雄のように描かれるのもそんな理由からなのかもしれない。
歴史は権力者の都合のいいように書かれるというが、その通りだと思う。明治維新についても然り、太平洋戦争についても安倍政権が続くと現在とは逆の見方が出てくるのだろう。江戸時代は徳川の絶対政権であったので、幸村は非合法な出版でしか活躍の場を与えられなかった。しかし、江戸時代も後半になると「敵ながらあっぱれ」的な視点で幸村も復権してきた。松代藩内でも幸村顕彰の動きは江戸時代からあったようだ。
最近芥川龍之介の「薮の中」を読み直してみた。以前読んだ時の印象で、ものの見方は人によって違う。ずいぶん曖昧なものだということがその内容だと思っていたのだが、そういうことではないようだ。男が死んで女が生き残ったという事実があって、それぞれのモノローグを綴りあわせたような短編小説だが、その言っていることがそれぞれに違う。男は自分が殺したというもの、自殺なのだというもの、それが語るものの立場や都合によって微妙に違う。
真田幸村に評価にしても、いろいろな人に語らせればその都度違う。真実は一つではないのだ。
Posted by 南宜堂 at 09:16│Comments(0)
│雑記