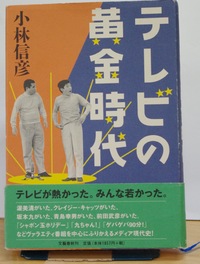2011年09月18日
カルメン故郷に帰る
長野と軽井沢を結ぶ第三セクターのしなの鉄道の売りは、何と言っても 小諸・軽井沢間の車窓から望む浅間山の雄大な眺めである。前身のJR信越線を走る特急の愛称は「あさま」といった。現在の長野新幹線の愛称も「あさま」である。
その浅間山の麓の村を舞台にした映画「カルメン故郷に帰る」は1951年に封切られた日本初の総天然色映画として知られている。監督は木下恵介、主演は先ごろ亡くなった高峰秀子であった。その高峰秀子の派手な衣装と、舞台となった浅間山麓の雄大で美しい自然が、総天然色のスクリーンいっぱいに描かれていて、当時の観客はその鮮やかさにさぞや度肝を抜かれたことだろう。
この映画には、浅間山や草軽電鉄の車両が頻繁に登場することから、てっきり信州にロケしたものだとばかり思っていたのだが、リリー・ カルメン(高峰秀子)らが降り立った駅名表示は「北軽井沢」とあることから、群馬県長野原町が舞台になっているのだということがわかった。浅間山は上信国境にそびえる山であり、草軽電鉄は長野県軽井沢町と群馬県草津温泉を結んでいたのだから、上州が舞台であっても全くおかしくはない。全てが信州のものだと思い込むのは、信州人の悪癖である。
草軽電鉄と言えば十数年前、「信州の廃線紀行」(郷土出版社)という本の取材で、軽井沢から草津温泉まで、廃止になった線路の跡をカメラマンとともにたどったことを思い出した。北軽井沢の駅舎は健在で、当時はスナックになっていたと思う。
草軽電鉄は、大正15年に全線が開通した高原鉄道で、当時のキャッチフレーズは「東洋唯一の高原電車 登る山道四千尺」というものであった。主な目的は草津温泉への観光客の輸送であったが、戦後になって国鉄長野原線の開業やバス路線の発達により乗客は減少し、台風の被害などもあって、昭和37年に残された草津温泉ー上州三原駅間が廃止となり、全線が廃線となった。
映画の中では、草軽電鉄は都会と山村を結ぶ文明の利器として登場するのだが、トロッコに毛の生えたようなその電車は、カブトムシのような形をしていて愛嬌はあるのだが、今から見ると文明とは程遠い存在であった。
家出同然に村を出たカルメン(高峰秀子)が、友だちのマヤと浅間山麓の故郷に帰って来るところからこの物語ははじまる。この映画に描かれる村は、草軽の駅はあるものの、純然たる田舎で、貧しいながらものどかな人々の生活が営まれていた。
東京で踊り子(ストリッパー)をしているらしいカルメンとマヤ、彼女たちとこの村の人々の生活感の食い違いが騒動を巻き起こすわけだが、監督木下恵介の視線は、親子の愛、夫婦の愛、さらにはひたむきに生きる山村の人々の暖かさを描くことを忘れていない。この映画唯一の悪人である丸十運送の社長にしたところで、借金のカタに強制的に取り上げた盲目の作曲家のオルガンを、最後には返してやる。根っからの悪人ではないのだ。
そんないい人ばかりの村、朝夕に仰ぐ浅間山が美しい故郷の村に、カルメンはなぜ留まることができないで、また出て行くのか。小さい頃に牛に蹴られて少し頭の働きが弱くなったカルメンは、村の中では生きていく術が見つけられず、家出同然に村を出る。都会は彼女を受け入れ、生活の途を与えてくれた。そんな彼女には田舎は、チョッピリ懐かしいが退屈な場所だったのだ。
大げさに言えば、カルメンが村を出て、都会で踊り子という仕事を得て、一応は成功するまでに至った軌跡は、戦後の日本がたどってきた成功の軌跡と重なっているのではないか。北軽井沢という土地が同じような軌跡をたどっている。軽井沢の北という、おそらくは避暑にきた都会の人がつけたであろう通称を、この土地の人は受け入れ、軽井沢を見習ってリゾート化を進めてきた。現在の北軽井沢には、しゃれたペンションやカフェ、別荘やゴルフ場、テニスコートが あちこちに点在する一大リゾート地に変貌している。映画に出てくるような、酪農やわずかばかりの土地を耕して生活している貧しい村というイメージとは大違いである。
丸十の社長は、村にリゾートホテルを誘致しようという計画を持っているのだが、それがその後に訪れた高度成長の中でどのように実現していくのか。映画の後の時代を知る私たちには、社長の構想が決して夢物語ではないということを知っている。映画の中の村だけではない。日本中の村が、丸十の社長のように発展を願って行動してきたというのが日本の戦後社会であった。
さらに私たちは、そんな浮かれた日本がバブルの崩壊により弾け飛んだ時代もまた知っている。高度成長の真っ只中にあった時、誰も口に出さなかった「かけがいのない地球」とか「自然を大切にしよう」とかいうスローガンが言われるようになった。しかし、これらの声は多分に情緒的であり、社会全体をおおうほどのものではなかった。いまだに成長神話が幅をきかせていたのである。
今年の3月11日、福島の原発事故は成長の果てに文明が行きつく先の姿というものを、まざまざと見せつけられた。それでも懲りない人たちはいる。日本の飽くなき成長のためには原子力発電所は絶対に必要だという声があちらこちらから聞こえてきているのである。
その浅間山の麓の村を舞台にした映画「カルメン故郷に帰る」は1951年に封切られた日本初の総天然色映画として知られている。監督は木下恵介、主演は先ごろ亡くなった高峰秀子であった。その高峰秀子の派手な衣装と、舞台となった浅間山麓の雄大で美しい自然が、総天然色のスクリーンいっぱいに描かれていて、当時の観客はその鮮やかさにさぞや度肝を抜かれたことだろう。
この映画には、浅間山や草軽電鉄の車両が頻繁に登場することから、てっきり信州にロケしたものだとばかり思っていたのだが、リリー・ カルメン(高峰秀子)らが降り立った駅名表示は「北軽井沢」とあることから、群馬県長野原町が舞台になっているのだということがわかった。浅間山は上信国境にそびえる山であり、草軽電鉄は長野県軽井沢町と群馬県草津温泉を結んでいたのだから、上州が舞台であっても全くおかしくはない。全てが信州のものだと思い込むのは、信州人の悪癖である。
草軽電鉄と言えば十数年前、「信州の廃線紀行」(郷土出版社)という本の取材で、軽井沢から草津温泉まで、廃止になった線路の跡をカメラマンとともにたどったことを思い出した。北軽井沢の駅舎は健在で、当時はスナックになっていたと思う。
草軽電鉄は、大正15年に全線が開通した高原鉄道で、当時のキャッチフレーズは「東洋唯一の高原電車 登る山道四千尺」というものであった。主な目的は草津温泉への観光客の輸送であったが、戦後になって国鉄長野原線の開業やバス路線の発達により乗客は減少し、台風の被害などもあって、昭和37年に残された草津温泉ー上州三原駅間が廃止となり、全線が廃線となった。
映画の中では、草軽電鉄は都会と山村を結ぶ文明の利器として登場するのだが、トロッコに毛の生えたようなその電車は、カブトムシのような形をしていて愛嬌はあるのだが、今から見ると文明とは程遠い存在であった。
家出同然に村を出たカルメン(高峰秀子)が、友だちのマヤと浅間山麓の故郷に帰って来るところからこの物語ははじまる。この映画に描かれる村は、草軽の駅はあるものの、純然たる田舎で、貧しいながらものどかな人々の生活が営まれていた。
東京で踊り子(ストリッパー)をしているらしいカルメンとマヤ、彼女たちとこの村の人々の生活感の食い違いが騒動を巻き起こすわけだが、監督木下恵介の視線は、親子の愛、夫婦の愛、さらにはひたむきに生きる山村の人々の暖かさを描くことを忘れていない。この映画唯一の悪人である丸十運送の社長にしたところで、借金のカタに強制的に取り上げた盲目の作曲家のオルガンを、最後には返してやる。根っからの悪人ではないのだ。
そんないい人ばかりの村、朝夕に仰ぐ浅間山が美しい故郷の村に、カルメンはなぜ留まることができないで、また出て行くのか。小さい頃に牛に蹴られて少し頭の働きが弱くなったカルメンは、村の中では生きていく術が見つけられず、家出同然に村を出る。都会は彼女を受け入れ、生活の途を与えてくれた。そんな彼女には田舎は、チョッピリ懐かしいが退屈な場所だったのだ。
大げさに言えば、カルメンが村を出て、都会で踊り子という仕事を得て、一応は成功するまでに至った軌跡は、戦後の日本がたどってきた成功の軌跡と重なっているのではないか。北軽井沢という土地が同じような軌跡をたどっている。軽井沢の北という、おそらくは避暑にきた都会の人がつけたであろう通称を、この土地の人は受け入れ、軽井沢を見習ってリゾート化を進めてきた。現在の北軽井沢には、しゃれたペンションやカフェ、別荘やゴルフ場、テニスコートが あちこちに点在する一大リゾート地に変貌している。映画に出てくるような、酪農やわずかばかりの土地を耕して生活している貧しい村というイメージとは大違いである。
丸十の社長は、村にリゾートホテルを誘致しようという計画を持っているのだが、それがその後に訪れた高度成長の中でどのように実現していくのか。映画の後の時代を知る私たちには、社長の構想が決して夢物語ではないということを知っている。映画の中の村だけではない。日本中の村が、丸十の社長のように発展を願って行動してきたというのが日本の戦後社会であった。
さらに私たちは、そんな浮かれた日本がバブルの崩壊により弾け飛んだ時代もまた知っている。高度成長の真っ只中にあった時、誰も口に出さなかった「かけがいのない地球」とか「自然を大切にしよう」とかいうスローガンが言われるようになった。しかし、これらの声は多分に情緒的であり、社会全体をおおうほどのものではなかった。いまだに成長神話が幅をきかせていたのである。
今年の3月11日、福島の原発事故は成長の果てに文明が行きつく先の姿というものを、まざまざと見せつけられた。それでも懲りない人たちはいる。日本の飽くなき成長のためには原子力発電所は絶対に必要だという声があちらこちらから聞こえてきているのである。
Posted by 南宜堂 at 10:09│Comments(0)
│雑記